物質の構成
最初に物質とはなにか、それがどのように成り立っているかについて学ぶ。
物質とは
"What is mind?" "No matter."
"What is matter?" "Never mind."
--Thomas Hewitt Key (1799-1875)
「心とは何だ」「たいしたものではない」--物ではない
「物とは何」「気にするな」--決して心ではない
―トマス・H・キー (1799-1875)
なんとも、含みのある名言ですね。現在は人の心すら物質の働きに由来することが理解されてきました。科学では心理学、医学、生物学、化学とあらゆる手段で、心の仕組みすら理解されつつあります。
化学は、英語でChemistryと呼ばれ、物理(Physics)とともに、現在の自然科学の最も重要な基礎をになう分野です。化学では、この世に存在する物質について、「何でできているの?」「どういうふうに組み立てられているの?」という、人類が知能を持つようになって一番最初に思ったであろう疑問を、科学という手法を使って解決しようとする分野です。
物質の構成
純物質と混合物
海水浴に行ったとき、海水には目で見えるような色々なものが混じっているのは知っているでしょう。中学校で習ったようにプランクトンや、海草の切れ端、この付近の瀬戸内海の海水なら、雲母のかけらもたくさん浮かんでいるでしょう。
この海水をろ紙でこして目に見えるものをすべて取り除いても、さらにそれを蒸発させれば固形物が取り出せます。
一見純粋に見えても、色々なもの、海水なら塩や水が交じり合っています。このように蒸発させたり、ろ過したりする、物質が異なる物理的な性質を持つことを利用して分離する=物理的な方法で分けられるものを混合物と言います。
物質を分ける。
物理的な分離方法には次のようなものがあります。
- ろ過
- 液体や気体と固体、あるいは粒子の大きさで分離する。
- 小中学校で行った'ろ過'など。ロートとろ紙を使った'正しいろ過の正しい方法'の方法も読んでおくこと。
- 逆浸透膜による海水から水を取り出すのもろ過の一種
- 蒸留
- 沸点の違いを利用して分離する。
- 醸造酒から蒸留酒を取り出すのも蒸留の応用である。ただし水とアルコールのように沸点が近く互いに溶け合う物質は蒸留では完全に分けることはできない。通常の蒸留方法ではせいぜい50パーセント程度の濃度のものしか得られない。そのため蒸留酒の濃度もそれ以下のものしかない。
- 再結晶
- 溶解度の違いや、融点の違いを利用して結晶を作らせて分離する。
- 中学校の教科書に載っていた明礬(明礬)の結晶も再結晶の一種である。
- 抽出
- 溶媒による溶解度の違いを利用して分離する方法
- 水を使って水に溶けるものだけを取り出すなど。
- クロマトグラフィー
- 分配率や吸着や拡散速度の違いを利用して分離する。
身近で観察できる具体的な例
意外と身近でこのような作用は見かけていたりする。たとえば汚れた水溜りに出来た氷の結晶、こぼれた醤油が蒸発してできる食塩の結晶、気が抜けた炭酸飲料・・・。
このように、物質という大きなグループは、混合物と純物質に分けられ、混合物は分離精製することによって純物質にすることができる。
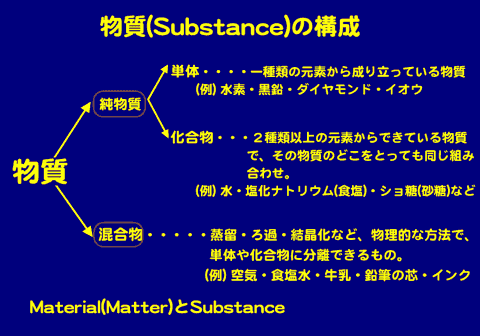
大部分の物質は混合物と考えてよいが、中学校でも習ったように、蒸留やろ過、再結晶などの色々な方法を使って、共通の性質だけを持ったものに分離して精製することができる。
時間があれば、クラスによってはここでそれぞれの精製方法について簡単に説明する。各科の内容にあわせて、説明する内容を変える。
ペーパークロマトグラフィー
サインペンの黒には何種類の染料が使われているかを簡単なペーパークロマトグラフィーで調べてみよう。
今回は、ろ紙を使ったペーパークロマトグラフィーを行う。詳しい手順はマニュアルを参照する。
純物質とは?
ここで、混合物とは何?純物質とは何?と聞かれたとき、
「混じりけのない物質が純物質で、純物質が混ざったものが混合物」という説明は、間違ってはいないけど、純物質や混合物の説明にはなっていない。「男は女でない、女は男ではない」と同じで堂々めぐり(循環論法)だよ。 「混合物は純物質が混ざったもので、純物質はそれ以上物理的方法で分けられない物質」
きちんと理解しておこう。
そこで、実際に思いつく身の回りの物質を分類してみよう。
身の回りの色々な物質を実際に分類してみよう。これは実際にやってみると意外と難しい。
純物質・混合物・単体・元素のこと
言葉の定義で、混乱してしまう所だが、きちんと理解しておこう。
